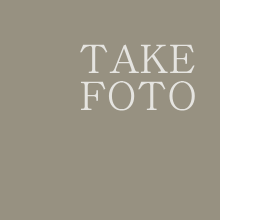古典写真技法とは

カーボンプリント
1855年にカーボン印画の発明者として一般に認められているフランスのルイ-アルフォンス・ポアトヴァンによる顔料とクロム酸塩の研究が行われました。
この印画法の特徴は、顔料の色を選択でき、ネガの階調をよく再現でき、耐久性のよいプリントを作成できることです。
この印画法は重クロム酸ゼラチンの光硬化性を利用しています。まずゼラチン溶液に重クロム酸塩を溶解し、これにカーボンまたは顔料を混合して紙に塗布し、感光性を持たせたカーボンティッシュを作る。カーボンティッシュにネガを密着して、露光させると、露光量に比例してゼラチン膜が硬化する。このティッシュと紙を密着させ、温湯に入れると硬化していないゼラチンが溶け出し、紙に画像が残る。

塩化銀紙 salted paper
1830年代に、塩化銀を塗った紙の上に半透明の物体を置いて影絵を焼き付けるフォトジェニックドローイング(Photogenic drawing 光で描く)と呼ばれる方法が、イギリスのウィリアム・ヘンリー・タルボット(William Henry Fox Talbot)により発明され、塩化銀紙による印画の始まりとなりました。
1844年から分冊で出版されたタルボットの「The Pencil of Nature (自然の鉛筆)」は、塩化銀紙のプリントが多数添付され、写真を使った最初の本です。
塩化銀紙は、塩化ナトリウムを紙の繊維にしみこませて、硝酸銀溶液を刷毛塗りする。これで塩化銀が生成され、紙の繊維にからんだ状態になる。塩化銀は光にあたると分解して銀を析出し、この銀が画像を形成する。光があたらなかった部分に残った塩化銀をチオ硫酸ナトリウムで溶解すると、画像は定着されて安定します。

鶏卵紙 albumen print
1839年ダゲールによって公表された、最初の実用的な写真術である「ダゲレオタイプ」に始まる写真の歴史の中で、19世紀半ばから20世紀初頭までの約50年間、もっともポピュラーだった写真印画法であり、数多くの写真が現在まで残されています。
鶏卵紙は、紙などの表面に「卵白に塩を加えた液」を均一に塗り、これを乾燥した後に「硝酸銀溶液」を塗布して、感光性をもたせたものであり、感光度は極めて低く(現在の印画紙の数万分の一)、引き伸ばしではなく、太陽光による密着焼付けを行います。
こうしてできたプリントの色調は赤褐色のセピア調で階調が美しく、紙の材質、卵白濃度、焼き付けの程度などによって、光沢、階調、最高濃度などを調整します。
なお本来のアルビューメンプリントは耐久性が低いので定着前に金調色を施しますが、
本来の色調を変えたくない場合、画像安定剤「Agガード」を使用しています。

アンソタイプ anthotype print
アンソタイプ(ギリシャ語で花の意)とは、植物や果実などを染料とする印画法で、
19世紀初頭イギリスのジョン・ハーシェルが発案したもので、当時のプリントが今でもの残っています。
環境に負荷をかけないプロセスです。

青写真 cyanotype print
サイアノタイプは、1842年に天文学者ハーシェルが発明した写真法。
この方法は、第二鉄塩が光照射により第一鉄塩に変化する性質を利用していて、第一鉄塩が、フェリシアン化カリウムと反応してタンブルブルーを生じると、光の照射量に応じて青い色の濃度変化が現れます。(ネガーポジ方式)
このプリントは、処理が比較的簡単で安価であり、しかも耐久性もあることから、19世紀から最近まで建築図面などに広く使用されました。

カリタイププリント kallitype print
カリタイプは、1889年にイギリスのニコルにより発表されました。
kalliとは、ギリシャ語でbeautifulの意味。
感光主剤にシュウ酸第二鉄と硝酸銀用います。光の作用でシュウ酸第二鉄がシュウ酸第一鉄に還元されされ、
これが水中に共存する硝酸銀を還元して銀画像を形成する。
焼き出し印画であり、画像の色を鮮やかにするため、焼き付けた後で酒石酸カリウムナトリウムや
ホウ酸ナトリウムなどを含む現像液で処理する。くえん酸ナトリウムで処理すれば、セピアブラウン、
くえん酸アンモニウムで処理すれば、レディッシュマロンなど、現像液によって色調を変化させることができる。
長期保存するには定着後に金調色を施しますが、本来の色調を維持したいときはAGガードを使用します。

バンダイクプリント vandyke print
バンダイクプリントは、カリタイプの一種だが、カリタイプのような現像を
必要とせず、茶色の色調の印画を作ることができる。
感光主剤はクエン酸鉄(Ⅲ)アンモニウムと硝酸銀に、酒石酸を用いる。
長期保存するには定着後に金調色を施しますが、本来の色調を維持したいときはAGガードを使用しています。
参考資料
「手作り写真への手引き」荒井宏子著 写真工業出版社 1997
「写真技法と保存の知識」ベルトラン・ラヴェドリン著 青幻舎 2017
「The Book of ALTERNATIVE PHOTOGRAPHIC PROCESSES」Christopher James CENGAGE Learning 2016
「PHOTOGRAPHIC ALTERNATIVE PROCESSES」JILL ENFIELD Routledge 2020
copyright©2012 TAKEFOTO all rights reserved.